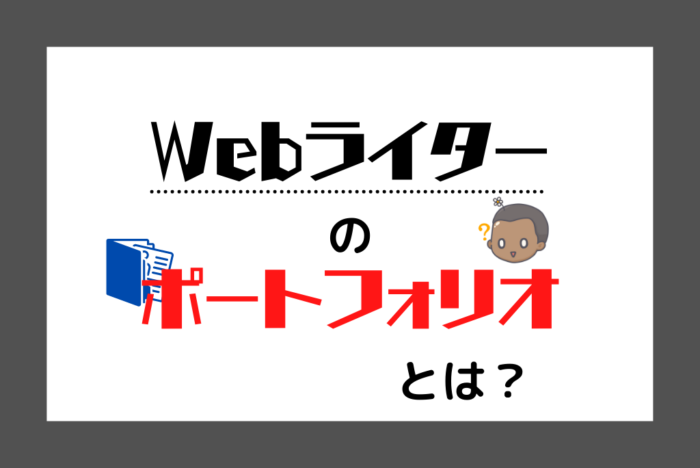よーし!Webライターでガンガン稼いじゃうぞ!
Webライターになるときは、誰しもが大きな期待を胸に抱いています。
でも、実際にはじめの一歩を踏み出すと、こんな悩みばかり。
- うまく自己PRができない
- 提案文すら通らない
- 全然案件が受注できない

もう、Webライターなんて辞めちゃおう
ちょっと待って。
そう考える前に、ポートフォリオを作ってみましょう。
ポートフォリオは、誰でも簡単に作れるものです。
でも、実際に作っている人は限られています。

稼いでいる人は、ほとんど自分のポートフォリオをもっているよ!
この記事では、Webライターのポートフォリオとはなにか、作るポイントやオススメのサービスについて紹介します。
この記事を読めば、アナタもWebライターとして一歩ステップアップできること間違いなし!
一緒に、Webライター生活を楽しみましょう!
Webライターのポートフォリオとは?
Webライターのポートフォリオとは、自分がこれまでに手掛けた「作品集」のことです。
主に、過去に自分の書いた記事のURLを記載したり、どんなメディアに記事を書いたのかを記載したりします。
もともと「ポートフォリオ」はデザイン業界で使われていた言葉です。
デザイナーが過去に作った自分の作品をまとめた作品集を、「ポートフォリオ」と呼んでいました。
この言葉が、Webライター業界でも使われるようになったのです。
Webライター業界もデザイン業界も、これまでの自分の実績を口や言葉だけで表現するのが難しい世界です。
そこで、自分の作品を「ポートフォリオ」としてまとめます。
そうすれば、自分の実績や能力が見えやすい形になって、営業活動をスムーズにすることができるようになります。
ポートフォリオは、Webライターとして活動をする中で、情報がたくさん書かれた名刺のような役割をしてくれるわけです。
Webライターにポートフォリオが必要な理由
ポートフォリオはWebライターに必須とも言えるものです。
しかし、実際はポートフォリオを作らずに活動している人も多くいます。
それは、ポートフォリオの大事さを理解していない人が多いからですね。
そこで、Webライターにポートフォリオが必要な理由を3つに絞ってご紹介します。
- クライアントが発注の判断に使う
- Webライター側から営業がかけやすくなる
- 文字単価の交渉にも使える
一つずつ見ていきましょう。
クライアントが発注の判断に使う
ポートフォリオは、クライアントがどのWebライターに発注するか決める判断材料に使われます。
クライアントは、一定の予算の中から、可能な限りスキルの高いWebライターに仕事を依頼しようとします。
ですから、実際にWebライターにテーマを与え、文章を書いてもらう「テストライティング」があるわけです。
ポートフォリオをもっていれば、過去に書いた自分の記事をスキルの証明書としてクライアントに提示できるようになります。
案件にもよりますが、ポートフォリオを示せばテストライティングを免除してくれるクライアントもいます。
高単価の案件では、最初からポートフォリオの提出が義務になっている案件もあります。
より仕事を効率良く受け、高単価の案件を受注していくためには、ポートフォリオの作成が必要になってくるわけです。
Webライター側から営業がかけやすくなる
Webライターの仕事のとり方は、クラウドソーシングだけではありません。
Twitterで募集されていることもあれば、実際にWebメディアにライターとして志願することもあります。
当然、自分がどれだけのスキルをもっているのかアピールする必要があります。
すべての営業で、一から自己PRの文章を作っても良いのですが、どうしても非効率的です。
最初から、自分のスキルを見せられるポートフォリオがあれば、営業するときに一々文章を書く必要はなくなります。
文字単価の交渉にも使える
Webライターとしての収入を上げるには、労働時間を増やすか、文字単価を上げる必要があります。
労働時間は本人のやる気で増やせますが、文字単価はそう簡単にはいきません。
ですが、ポートフォリオがあれば文字単価の交渉もしやすくなります。
文字単価とは、Webライターがどの程度の文章を書けるかを基準につけられています。
誰でも書ける案件なら単価は低くなりますし、書けるWebライターが限られる難しいテーマの案件なら単価はあがります。
クライアントがWebライター一人ひとりの実力をしっかりと認識できていれば問題ありません。
ですが、現実は甘くありません。
自分でリサーチから構成ができるのか、SEOの知識はあるのか…。
Webライターのスキルを示す指標は無数にあり、すべてをクライアントがWebライターの文章から見抜くことは不可能です。
過去に検索順位1位の記事を書いたことがあれば、SEOの知識の証明になります。
構成から納品まで、すべてを一人でこなした仕事があるなら、任せられる仕事の範囲が広いライターだと示すことができます。
クライアントからしても、「このWebライターはこんなことができるのか」と、スキルを再確認できるようになります。
今の文字単価に見合わないようなスキルをもっているなら、ポートフォリオでしっかりとアピールすれば、文字単価を上げることができるかもしれません。
単価に不満がある人は、一度ポートフォリオの作成を検討してみましょう。
Webライターのポートフォリオの作り方

じゃあ、さっそくポートフォリオを作るぜ!
こんな風に意気込んでも、何から始めればいいのかわかりませんね。
ここでは、ポートフォリオに書くことを具体的に解説していきます。
ポートフォリオに書くことは、ざっくりと次の通りです。
- 自己紹介/経歴
- 得意分野
- 実績
- 執筆記事例
- 依頼の条件
一つずつ詳しくご説明していきます。
自己紹介/経歴
必ず載せなければいけないのが、自己紹介や経歴です。
自己紹介や経歴の中でも、次の項目は載せるようにしましょう。
- ペンネーム、もしくは本名
- 専業か副業か
- Webライターを始めたきっかけ
- Webライターを始めた時期
専業なのか副業なのかは、クライアント側からすると、Webライターがどれほどの作業量をこなせるのかを見る指標になります。
わかりやすいように、明示しましょう。
Webライターを始めたきっかけは、その人がWebライターという仕事にどれほど熱量をもっているかを見るのに使われます。
たとえば、「なんとなく、楽そうだと思って始めました」という人と、「昔から文章を書くのが大好きで始めました」という人がいたとしましょう。
アナタは、どちらの方に仕事を任せたいと思いますか?

私は、後者だね
このように、Webライターをはじめたきっかけも、Webライターの素質を見るのに利用することができます。
始めた時期については、自分のキャリアを示すのに必要です。
仮に始めたばかりでも、恥ずかしがることはありません。
むしろ、不自然に隠す方がクライアントの不信を招きます。
素直に書くようにしましょう。
得意分野
自分がWebライティングで書ける得意分野を書きましょう。
具体的であればあるほど良いです。
たとえば「健康」と書くよりも、「ダイエット」「運動」と書いた方が伝わります。
さらに言えば、「ダイエット」よりも「低糖質ダイエット」「食べるだけダイエット」、「運動」よりも「筋トレ」「水泳」「サッカー」と書いたほうが、より具体的にアナタの得意分野が伝わるでしょう。
この得意分野は、Webライターとして書いたことのある分野でなくても大丈夫です。
本業や、過去の経験から「このテーマなら書ける」と思ったテーマは、遠慮なくポートフォリオに入れましょう。
まったく知識のない人と、多少なり経験のある人が書く記事の質は違います。
この差が、Webライターとしての成果につながることもあります。
実績
これまでにWebライターとして活動してきた人は、これまでの実績を列挙しましょう。
いくつか、例を挙げてみます。
- 転職系サイトに書いた記事が、SEOで1位を獲得
- 自身の書いた記事が、サイト内の人気ランキングで1位に
- IT系企業のオウンドメディアに継続的に記事掲載中
他にもさまざまな例が考えられます。
自分の書いた記事がどのような結果を生んだのか、どれほどの執筆量があるのかといった点に注目すると、書きやすくなります。
仕事で大量のビジネス文書の作成を書いているならそれもよし。
タイピングに自信があるなら、実際にタイピングソフトで速度を測り、記載するのもいいかもしれません。
もし、本当にどうしても実績が見つからないという人は、クラウドワークスが実施しているWEBライター検定の3級を受けてみましょう。
無料で受けられる資格試験ですが、無料とは思えないほど充実した講義動画が見られます。
合格率は5%と狭き門なので、受験対策にしっかりと取り組む必要があります。
ですが、合格することができれば、それは立派な実績になります。
どうしても自分の実績が思いつかない人は、WEBライター検定の受験を検討してみましょう。
Webライター検定3級の記事は、>>コチラからどうぞ!
記事執筆例
ポートフォリオで最も重要な要素です。
これまでに書いてきた記事の中から、自信のある記事をいくつか選び、ポートフォリオに書きましょう。
もし、自分でブログを運営している人なら、ブログ記事でも問題ありません。

私も、自分のブログ記事を載せているよ
ポイントは、自分に文章を書くスキルがどれほどあるかを示すことです。
- 自分が担当した範囲
- かかった時間
- 気をつけたポイント
こういった点を合わせて書くことで、より明確にクライアントへ自分のスキルを伝えることができます。
依頼の条件
依頼を受ける際の条件も、忘れてはいけません。
- 文字単価
- 1週間や1ヶ月で書ける量
- 記事を納品する際のデータ形式
この3点は忘れずに書きましょう。
実際にクライアントが発注する際に、基準となる項目です。
もし、連絡がとれる時間や働ける期間に制限があるなら、隠さず書きましょう。
Webライターは、基本的に実力と信頼の世界です。
いくら実力があったとしても、契約時に不利な情報を隠していたら、一気に信頼を失います。
Webライター側もクライアント側も納得して仕事を進められるように、仕事や依頼に関する条件は、悪い点も含めてポートフォリオに書くようにしましょう。
Webライターのポートフォリオ作りにオススメのサービス
ポートフォリオを作成する際には、自分のWebサイトか無料サービスを利用しましょう。
Wordなどのテキストデータを利用することもできますが、オススメはしません。
Webサイトや無料サービスなら、URLを共有するだけでクライアントに見てもらうことができます。
また、ポートフォリオはWebライターとしての活動歴が長くなればなるほど、更新する機会が増えます。
一度手渡した後は修正が難しい文書やワードではなく、オンラインで修正ができるサービスを使うようにしましょう。
Webライターがよく利用しているサービスは、次の4つです。
- WordPress
- note
- 無料ブログ
- ペライチ
一つずつ、詳しくご紹介します。
WordPress
1つ目が、WordPressです。
WordPressとは、プログラミングの知識がない人でも簡単にWebサイトを作れるサービスです。

私もその一人だよ!
Webライターには、ライターとしての活動と合わせて自分のメディアやブログを運営している人も多くいます。
自分のメディアやブログがあれば、そこに自分のポートフォリオを作ることができます。
デザインや装飾を自分の思う通りにできるため、より魅力的なポートフォリオを作りやすいサービスです。
WordPressがオススメなのは、ポートフォリオに使えるからだけではありません。
自分のメディアやブログを運営すれば、自由に記事を執筆する環境が手に入ります。
アフィリエイトを活用すれば、Webライターとは別の収入源につなげることもできます。
また、メディアやブログ運営をする中で身につく知識は、いずれもWebライターとしてのスキルアップに欠かせないものです。
SEOやWebマーケティング、セールスライティングといった実践的なテクニックを、メディアやブログ運営の中で手に入れられるというわけです。
もし、Webライターとしてさらにスキルアップをしていきたい人は、自分のメディアやブログをもつことを考えてみましょう。
note
無料サービスの中でよく用いられるのが、noteです。
Webライター以外にも、多くのクリエイターが利用するプラットフォームですね。
簡単な文字装飾や画像利用もできるため、それなりに見栄えの良いポートフォリオを作ることができます。
ただし、デザインのカスタマイズ性はほとんどないため、個性を出すのは難しい点に注意しましょう。
無料ブログ
無料ブログでポートフォリオを作ることもできます。
主な無料ブログサービスは、次の通りです。
サービス提供者側が用意している枠組みの中でなら、比較的自由にポートフォリオを書くことができます。
ただし、WordPressで作る自分のメディアやブログと比べると、やはりカスタマイズ性が落ちます。
もちろん記事を書くこともできますが、規定上、アフィリエイトができない場合もあることに注意が必要です。
ペライチ
ペライチも、自分のWebサイトを作ることができるサービスの一種です。
WordPressでサイトを開設する際には、自分でサーバーを用意し、ドメインを取得する必要があります。
このため、多少の初期費用と手間がかかることになります。
ペライチの場合は、サーバーとドメインの用意が必要ありません。
ただし、メディアやブログのように、複数ページを制作する機能は有料です。
ポートフォリオ用の1ページなら、無料で作れます。
自身でメディアやブログを運営する気がなく、ポートフォリオだけ作りたいのなら、ペライチの利用でも問題ありません。
隠れたオススメ!「#106members」
比較的新しいサービスで、Webライター向けオンラインサービス「#106members![]() 」があります。
」があります。
無料の会員制サービスで、登録すればオンライン講座のお試し視聴やDiscordのコミュニティ参加ができる他、ポートフォリオの作成もできます。
note以上に自由な編集ができるため、デザインにこだわりたい人にはオススメです。

不安な人も大丈夫!
実際に私が試してみたレビュー記事もあるよ!
興味のある方は、以下のリンクからお読みください。別タブで開きます。
徹底レビュー!Webライター向けサービス「#106members」の評判は?
ライバルに差をつける!Webライターのポートフォリオの作り方
ポートフォリオを作れば、それだけで多くのWebライターよりも一歩リードすることができます。
しかし、高単価だったり、多くの仕事を引き受けたりしているWebライターは、当たり前のようにポートフォリオを作っています。
そこで重要になってくるのが、ライバルのWebライターと差をつけられるようなポートフォリオの作り方です。
この記事では、以下の3つのポイントを紹介します。
- Webライター以外の活動も書く
- 最新の情報を入れる
- 情報の見せ方を工夫する
それぞれ、詳しくご説明します。
Webライター以外の活動も書く
自己紹介や経歴で、Webライター以外の経歴や活動も書くようにしましょう。
とくに、弁護士、公認会計士といった国家資格をもっている人や、飛行機のパイロット、大学教授のような絶対数の少ない職業についている人はチャンスです。
このような人々は、一般の人と比べると特定の分野に関する専門的な知識をもっています。
Webライターが記事にする分野は数え切れないほど多数あります。
ですが、専門的な知識が必要な記事を書けるWebライターは限られています。
自分の価値をアピールするためにも、しっかりと自分についてポートフォリオに書き込みましょう。
また、このように専門性が高い職業でない人でも、可能な範囲で学歴や職歴、なりわいとしてきた仕事について書きましょう。
繰り返しになりますが、Webライターが書く記事の内容は非常に幅広いものです。
職業として一般的な「営業職」について書くこともあれば、「専業主婦/夫」について書くこともあります。
アナタがどんな経歴でも、その経験を求めているクライアントは必ずいます。
「自分なんて、たいしたことない」と思わずに、堂々と経歴をポートフォリオに書いてやりましょう。
最新の情報を入れる
ポートフォリオは常に更新し、最新の情報を入れるようにしましょう。
Webライターとしての活動を続ければ続けるほど、自分のライティング技術はどんどん向上していきます。

私もかなり文章には自信あるけど、1年前の記事を見ると「ひどいもんだ!」って思うよ!
また、昔の記事しか載っていないポートフォリオを見たクライアントの気持ちを考えましょう。

この人、最近は仕事していないのか…?
こんな風に疑われかねません。
- 自分の最新のライティングスキルを見せる
- 現在も鋭意Webライターとして活動している
この2点をアピールするためにも、定期的にポートフォリオは更新するようにしましょう。
情報の見せ方を工夫する
情報の見せ方を工夫しましょう。
時々、ただ過去の経歴や実績を並べているだけのポートフォリオを見かけます。
もちろん、無いよりはマシです。
ですが、可能なら、解説文をつけたり表にしたりして、読者となるクライアントに伝わりやすいを考えましょう。
他にも、以下のような工夫が考えられます。
- オリジナルの図を入れる
- 写真をつける
- 連絡先や連絡フォームを載せる
Webライターの仕事の本質は、ネットや現実世界にあふれている情報を集め、取捨選択し、読者にとってわかりやすい文章にし、「記事」を世に送り出すことです。
そのWebライターのポートフォリオが、読者の見やすさや理解しやすさを考えていない、ただの情報の羅列だったら、アナタはどう感じますか。
Webライターのポートフォリオの読者は、クライアントです。
クライアントに自分のスキルを見せるのがポートフォリオを作る一番の目的ですから、情報の見せ方を妥協してはいけません。
Webライターがポートフォリオを作る時の注意点
Webライターがポートフォリオを作る時に、気を付けなければいけない点があります。
必ず気をつけたいのは、次の3点です。
- 誤字脱字をしない
- 記事を無断掲載しない
- 「履歴書」にしない
一つずつ、解説します。
誤字脱字をしない
Webライターとして、作品やポートフォリオに誤字脱字があるのは決して許されません。

時々考えの緩い人がいるよね。
でも、文章で食べていくのにそんな意識なのは論外だよ!
もちろん、Webライターも人ですから、100記事書いたら1回はミスが出ます。
ですが、理想はミスをゼロにすることです。
誤字脱字は、記事や情報の信頼性に直結します。
いかに立派な肩書のある人が、正確な情報を書いてあったとしても、すべての段落に誤字脱字があるような記事があるとしましょう。
アナタは、その記事に書かれていることを信頼できますか?
すこし大げさな例ですが、私たちが日常的に接しているWebコンテンツでも同じことが言えます。
一つくらいの誤字なら気にせず読み飛ばせるかもしれませんが、一つの記事に2箇所以上誤字脱字があると、その記事全体の信頼が地に落ちます。
Webライターの名刺とも言えるポートフォリオなら、なおさらです。
私は、文ブロの運営を通して、発注者としてWebライターに記事を発注しています。
発注者の立場から言えば、ポートフォリオに誤字がある時点でそのWebライターに頼む気はなくなります。

その人が書く記事の質が、信用できないからね!
記事に比べるとポートフォリオの誤字脱字チェックをしている人は少ないように思います。
更新のたび、意識的に校正校閲作業をするようにしましょう。
記事を無断掲載しない
記事の執筆例を掲載する際に、無断掲載しないように気をつけましょう。
Webライターが案件を受けて書いた記事は、ほとんどの場合、著作権が発注者側に移っています。
このため、Webライターが「自分の作品だ」とポートフォリオ上で宣伝することを嫌がるクライアントもいます。
もし、「この記事はぜひアピールしたい!」という記事があるならば、一度クライアントにポートフォリオへの掲載について確認をするようにしましょう。
また、この問題は自分でメディアやブログを運営している場合は発生しません。
自分のメディアやブログ用に自分で書いた記事の権利者は、自分です。
渾身の作品をメディアやブログに掲載するようにすれば、その記事をポートフォリオに組み込んで活用することができるようになります。
もし、アナタがWebライターとしてさらに活躍の場を広げたいなら、自分のメディアやブログを始めることも考えてみましょう。
「履歴書」にしない
自己紹介や経歴、実績を書くため、履歴書のように必要最低限の情報しかポートフォリオに書かないWebライターがいます。
非常にもったいないです。
情報を並べるだけではなく、理由を深く掘り下げたり、とくに注目してほしい点について詳しく書き込んだりするようにしましょう。
たとえば、自分の職歴を公開しているなら、「なぜその職業を選んだのか」「その職業でなにを学んだのか」などを書いてみましょう。
記事を掲載している場合は、「その記事はどんな特徴があるのか」「どういった点に力を入れて書いたのか」を書くべきです。
ただ情報を並べるだけでは、アナタがどんな人なのかをクライアントに伝えるのは難しいでしょう。
一つひとつの項目について、わかりやすい解説をつけて、より細かい情報をクライアントに知ってもらえるようにすべきです。
ポートフォリオの具体例
実際にWebライターのポートフォリオをいくつかご紹介します。
もってぃの場合
このブログの管理人、もってぃのポートフォリオはコチラです。
文ブロ内にポートフォリオ用のページを作り、公開しています。
URLをクライアントに送るだけで見てもらえるので、非常に重宝しています。
読者の利便性を意識し、見出しを見るだけで何を書いているかわかるようにした上で、ページ内を移動できる目次をつけています。
私の場合、Webライターの実績よりも、「新聞記者」という職業の方がセールスポイントになります。
そのため、新聞記者としての仕事についても細かく書くことを意識しました。
ふうかちゃんの場合
文ブロに寄稿してくれている、竹原ふうかちゃんのポートフォリオはコチラ。
noteを利用したポートフォリオです。
Webライターを始めるまでの経歴がかなり詳しく書かれています。
このため、発注者の立場で見ると、こんな風に感じます。

転職系の話題を書いてもらえそうだな

営業職の話を書いてもらおうかな
このように、ふうかちゃんに書いてもらうことができそうな記事を具体的にイメージすることができるわけですね。
ポートフォリオに具体的な経歴を書き込む重要さがわかりますね。
私が仲良くさせてもらっている、専業Webライターのハス山さんのポートフォリオをご紹介します。
>>コチラです。
Webライターとして累計4年間の積み上げがある方です。
その実績を、画像やクライアントからの評価を交えて丁寧にまとめています。
とくに、強調スニペットについて画像も使っているのは素晴らしいですね。
Webコンテンツを制作する上で、自分のコンテンツを検索エンジンで上位表示させた経験はかなりの強みです。
「まだ早い」。そんなこと言わず、ポートフォリオを作ろう
Webライターとして一歩ステップアップするには、ポートフォリオを作ることが欠かせません。
仮にWebライターとしての実績がなくても、自分の経歴や他の仕事の実績を書けば、十分に充実したポートフォリオが作れます。
「私にはまだ早い…」なんて言わず、さっそくポートフォリオを作ってみましょう。
これまでに、必死で提案文を書いてきた時間や、安い単価でテストライティングを受けてきたことがバカらしく感じるようになります。
充実したポートフォリオを作って、Webライターとして一旗あげちゃいましょう!