Webライティングやビジネス文書で重視されるのが、文章のわかりやすさです。
読者に情報を正確に、素早く理解してもらうためには、わかりやすい文章を書くのが一番です。
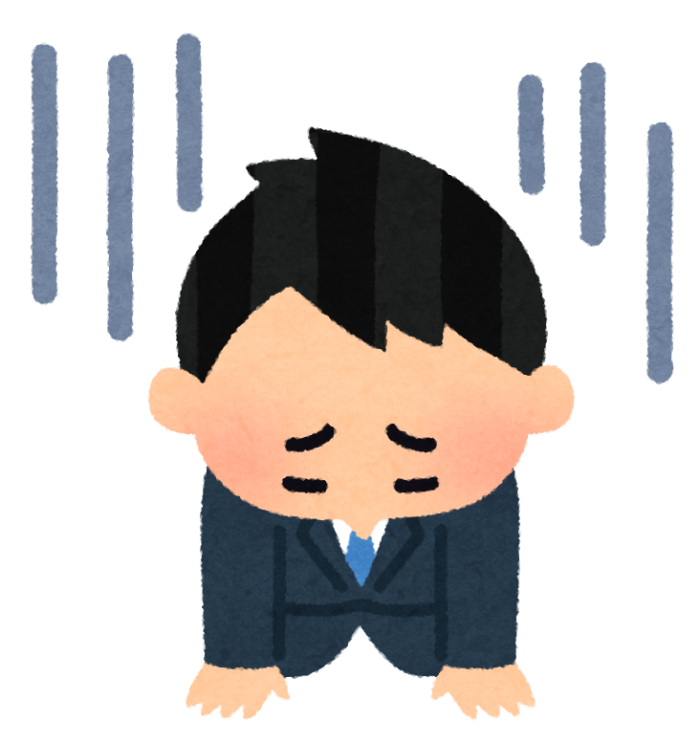
でも私、文章を書く才能ないから…
大丈夫です。
わかりやすい文章の書き方には、コツがあります。
コツさえ押さえてしまえば、誰でもわかりやすい文章を書けるようになります。
今回の記事では、現役の新聞記者としても働くWebライターが実践の中で身につけてきた、わかりやすい文章を書くためのコツをご紹介します。
少しでも理解しやすいように、楽しく読める例文もつけてあります。
ぜひ、じっくり読んでいってください。
わかりやすい文章の書き方には「コツ」がある
「文章を書く」ということについて話をすると、良く言われることがあります。

私、才能ないから…
はじめに言っておきます。
文章を書くことに、才能はいりません。
わかりやすい文章を書くコツを押さえ、繰り返し練習すれば誰でも書けるようになります。
確かに、小説や映画脚本のような芸術的な文章を書くには、才能が必要でしょう。
ですが、自分の経験や考え、知識を伝えるための文章を書くことには、才能はいりません。
必要なのは、次の2つの要素です。
- 文章を書くことに慣れているか
- 書くことのコツを知っているか
文章は書けば書くほど上手になります。
書き方のコツを押さえた上で経験を積めば、さらに成長の速度が上がります。
むやみに文章を書きまくる前に、ぜひこの記事で紹介するわかりやすい文章の書き方のコツを押さえてみてください。

自分でも驚くほど、わかりやすい文章が書けるようになるよ!
新聞記者が教えるコツ10選!分かりやすい文章の書き方
さっそく、わかりやすい文章の書き方のコツをご紹介します。
この記事で紹介するコツは、どれも私が新聞記者やWebライターとして執筆する時に心がけているコツです。

すべてを一度に意識するのは難しいかも!
何度も読んで、自分のものにしてね!
紹介するコツは、次の通りです。
- カッコつけない
- 文章は短く区切る
- 主語と述語は近くに置く
- 難しい言葉は使わない
- 音読のしやすさを重視する
- 「受け身」は使わない
- 「など」は極力使わない
- 形容詞には頼らない
- 代名詞は使わない
- 体言止めは使わない
一つずつ、みていきましょう。
カッコつけない
わかりやすい文章を書く上で一番大事にしたいのが、カッコつけないことです。
文章を書こうと思うと、なぜか頭の中の「私、賢い子」スイッチがオンになる人がいます。
特に、文章を苦手と思っている人ほどこの傾向があります。
文章を書くことを特別なことと思っているので、自分のことを頭良さそうに、カッコよく見せようとしてしまうわけですね。
この「カッコつける」という意識が、文章を書く上では最も邪魔なものです。
カッコつけた文章というのは、言い換えれば自分に酔った文章になりがちです。
なんとなく頭の良さそうな言葉を使ってみたり、情景を感じさせる言葉を使ってみたりする文章ですね。
こういった文章を書いてしまうと、無駄な情報が増え、一気に読みづらさが増します。
さて、それではカッコつけた文章がどのようなものになるのか、例文を見てみましょう。
かっこつけるために余計な情報を足して、結局文章で何を伝えたいのかがわからなくなっています。
カッコつけず、シンプルな言葉を選んで書くようにしましょう。
文章は短く区切る
一つの文章は、短く区切るようにしましょう。
ここでいう文章というのは、記事全体のことではなく、「一文」のことです。
特に文字制限のないWebコンテンツだと、いつまで続くか分からないほど長い文章を書く人がいます。
長い文章は読者にとっては苦痛です。
文章が長いと、読み終わった時に、文章のはじめに何を書いてあったのかわからなくなってしまいます。
結果、読者にとって何だかよくわからない文章になってしまうんですね。
1文の目安としては、どんなに長くても140字、可能なら50字までしぼることをおすすめします。
短い文章を書く心構えを、一文一義とも呼びます。
「一文の中に含む情報は一つにしましょう」という考え方です。
とくにWebライティングの世界では一文一義が基本とされています。

Webライターやブロガーは、忘れないようにしたい考えだね!
文章と文章をつなぐ「接続助詞」が多いですね。
一つの目安として、接続助詞で文章がつながっているところを区切るようにしましょう。

このおじさん、私が通っているジムに実在してるんだよね…
主語と述語は近くに置く
主語と述語を近くに置くのも重要です。
意識していないと、見落としがちなポイントであるため、注意しましょう。
主語・述語というのは、文章の中での言葉の役割関係のことです。
- ●●(主語)が▲▲する(述語)
- ●●(主語)は▲▲だ(述語)
こういったイメージですね。
わかりやすい文章についての記事なのに、いきなりわかりにくい話が出てきました。
とりあえず、こう覚えておけば大丈夫です。
文章の中で「は」「が」がつくのが主語。
この主語について、「何をしているのか」「どういう状態なのか」「そもそも何なのか」にあたる部分が述語です。
例を挙げてみます。
日本語の文章は、この主語・述語から成り立っています。
主語、述語の距離が離れていればいるほど、何を言いたい文章なのかがわかりにくくなります。
わかりやすい文章を書くためには、主語と述語の距離を近づけることが重要です。
ダメな例は、主語と述語が離れた位置にありますね。
近づけてみましょう。
難しい言葉は使わない
難しい言葉を使わず、なるべく簡単な言葉や表現に変えることも必要です。
難しい言葉とは、専門用語や業界用語、ビジネスシーンで使われるカタカナ語のことを指します。
専門用語を使うと、文字数は少なく、正しいことが書いてありそうな雰囲気の文章を書けます。
しかし、読者には伝わりません。
本や新聞、ネットの情報を読む時、一か所でも分からない単語が出てくると、読者の「読む」という行為はそこで止まってしまいます。
専門用語を含む、悪い例を見てみましょう。
わからない単語が出てくると、「この言葉はなんだろう?」と文章を読むのが止まってしまいます。
もしかしたら、単語を調べるためにネット検索をするかもしれません。
そのまま、ネットサーフィンをするかもしれません。

そうなると、せっかく書いた文章を最後まで読んでもらえないね…
難しい言葉を使わず、誰でもわかる簡単な言葉や表現に書き換えるクセを身に着けましょう。
専門用語を使うと書く側は楽なのですが、読者のためになりません。
難しい言葉を自分の中で噛み砕いて、誰にでも伝えられるようにしましょう。
音読のしやすさを重視する
口語に近い文章を書くときには意識すべきなのが、音読のしやすさです。
とくにWebライターやブロガーに当てはまるコツの一つでしょう。
音読のしやすさに影響するのは、主に次の3つのポイントです。
- 、(読点)
- 。(句点)
- 改行のタイミング
まず、ダメな例を見てみましょう。音読してみてください。
この例には、次のような悪いポイントがあります。
- 読点を使いすぎな部分がある
- 読点を使わなすぎる部分がある
- 不自然な改行がある

読点や改行を入れるタイミングがわからないよ・・・
こんな人は、声に出しながら文章を書いてみるようにしましょう。
息継ぎや、抑揚をつけるタイミングで読点や改行を入れるようにしてみてください。
上に挙げた例文を、声に出しながら打ち直してみます。
適切な箇所に読点や改行が入ったことで、だいぶスッキリしましたね。
自分が書いた文章を確認するときには、一度声に出すことをおすすめします。
文章の変な区切りだったり、そもそも変な構文になっていないか、気づくことができるはずです。
「受け身」は使わない
受け身を極力使わないようにするのも、わかりやすい文章を書くポイントです。
受け身の文章というのは、「(主語)が(述語)される」という構造の文のことです。
受け身の文章は、主語が省略されることが多くなります。
このため、書き手と読み手の間で主語についての解釈が分かれ、文章の意味が正確に伝わらなくなる可能性があります。
悪い例文から見ていきましょう。
私は、「マッチョ」が主語のつもりで上の文章を書きました。
しかし、受け身の文章では、主語が省略されることが多いです。
このため、読む人によっては全然違う情報を読み取ってしまう可能性があります。
こういう感じです。
この例文は、まだ単純な話ですから理解しやすいかもしれません。
しかし、難しい話の最中で受け身の文が出てくると、主語が何か、読者がわからなくなってしまいます。
受け身を使わないと意味が正確にならない場合以外で、受け身を使わないようにしましょう。
「など」は極力使わない
わかりやすい文章を書くためには、「など」の多用も避けるようにしましょう。
「など」「とか」といった言葉は文章をぼんやりさせてしまいます。
要所で使う分には問題ありません。
しかし、短い間隔で立て続けに「など」を使うと、途端に何を言いたいのかがはっきりしない文章が完成します。
「など」は極力使わず、しっかり言い切ることを心がけましょう。
などが立て続けに出てくるダメな例を見てみましょう。
「など」をたくさん使うとわかりにくい文章になるのは、読者が「他に何があるの?」と思う可能性があるからです。
読者に文章を読み進めてもらうためには、極力障害になる要素は取り除く必要があります。
たくさんの「など」はその筆頭です。
言い切っても問題がないのなら、「など」を使わずにしっかりと言い切る形で文章を書きましょう。
形容詞には頼らない
あいまいな形容詞に頼るのも、文章がわかりにくくなる原因の一つです。
たとえば、「美しい」という言葉の雰囲気を、みなさんはどう感じますか?

私は、真っ黒に焼けた筋骨隆々な上腕二頭筋を「美しい」と感じるよ!
おそらく、私と同じ感じ方をする人は、100人いたら1人か2人でしょう。
形容詞というのは、人によって受け止め方が違うものです。
あいまいな形容詞を使ってしまうと、書き手が伝えたいことと、読者が読み取ることに差が生まれる可能性があります。
次の文章を見てください。
「美しい」「複数の」という言葉は、読む人によって印象が変わる言葉です。
「美しい空」と聞いて、カンカンに晴れた空を想像する人もいれば、曇り空を思う人もいるでしょう。
「複数の」というのも、2人を想像する人もいれば、100人を想像する人もいます。
こういう認識のずれを避けるためには、あいまいな形容詞を使わずに、はっきりした意味を持つ言葉を使うことが重要になるわけです。
形容詞の中にも、ハッキリとわかりやすい意味の形容詞があります。
可能な限り、ハッキリした形容詞を使うことで、よりわかりやすい文章を書けるようになります。
代名詞は使わない
代名詞というのは、「これ」「それ」「あれ」「どれ」といった言葉です。
ひとまとまりの文章の中で、繰り返し同じ言葉を使うのを避けるときに使いますね。
代名詞は、うまく使えば文章をスッキリわかりやすくできます。
しかし、下手な使い方をすると一気に文章が崩れる諸刃の剣です。
下手な使い方の代表例が、「多用」ですね。
ダメな例を見てみましょう。
一文ごとに指示語が出てくると、非常にわかりにくい文章になることがわかりますね。
上手に使えば文章をわかりやすくできる指示語も、多用するとなんの話をしているのかわからなくなります。
もし代名詞の使い方に少しでも自信がないなら、まどろっこしくても、繰り返し同じ言葉を使うようにしましょう。
体言止めは使わない
体言止めも、あまり使わないようにするのが賢明です。
体言止めというのは、名詞で文章を終わらせる表現方法のことです。
体言止めは上手に使うと、文章にリズムを作ることができます。
このため、音読ができる文章を作るために使わざるを得ない場面もあります。
ですが、体言止めにも弱点があります。
それは、体言止めが、名詞の先にどんな言葉が続くのかを読者に想像させる表現方法であることですね。
わかりやすい文章を書くには、読者が文章を楽に読めるようにすることが重要です。
体言止めのように、続きを読者が想像しなければいけない表現方法は、読者にとって大きな負担になります。
これは、読み手にとって非常に疲れます。
体言止めが続く文章は、一見オシャレでテンポが良く見えても、読者を疲れさせるだけの文章になりかねないので気をつけましょう。
ダメな例を見てみましょう。
たったこれだけの文章でも意味を理解しようとすると、頭をフル回転させる必要があります。
確かに雰囲気やリズム感は良くなりますが、素直に「主語述語」の文章にした方がすっきり読める文章になります。
体言止めを使うにしても、それ以外に良い書き方がないときだけにしましょうね。
コツを押さえて、わかりやすい文章を書こう!
コツを押さえれば、誰でもわかりやすい文章を書くことができます。
この記事で紹介したコツを押さえながら、文章を書く経験を積んでいけば、どんどん文章力も身につけられるでしょう。
ただ、10個もあるコツを、いきなり同時にやろうとしても難しいはずです。
文章を書く練習をする中で、まずは一つのコツを意識しなくてもできるくらいに体になじませる。
それができたら、次のコツを意識する。それができたら、また次を――。
このように何度も練習を重ねていくのが、分かりやすい文章を書けるようになる一番の近道です。
わかりやすい文章を書く力は、一生の財産になります。
就職活動のES、社会人になった後のビジネス文書、社外とのメール。
小学生の時に書いたような「作文」は大人になると書かなくなります。
しかし、相手に何かを伝える文章はこれからもずっと書き続ける必要があります。
わかりやすい文章を書く力は、そんなときに輝くスキルです。
習得するのは大変ですが、一度身につけたらアナタの一生を明るくするスキルになるでしょう。

頑張って身につけてみよう!

